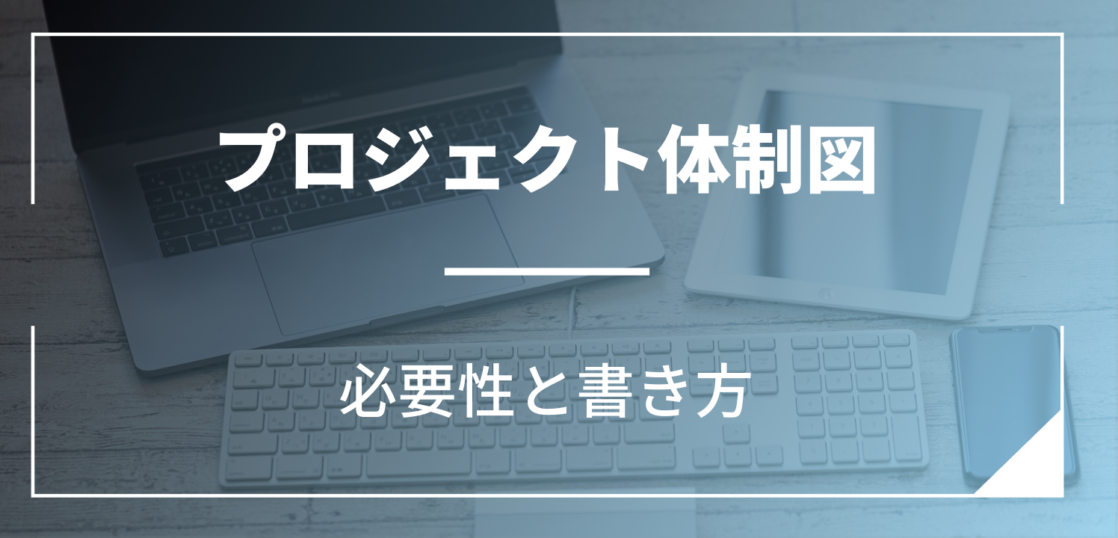企業におけるシステム開発業務は、一人ではなく複数人で行われる場合がほとんどです。
システム開発のプロジェクトメンバーとしてそれぞれが参画して、個々の役割のもと、スケジュールに沿って作業を進めていきます。
今回は、プロジェクトの統率を図るために重要な役割を持つプロジェクト体制図について、必要性と書き方をご紹介します。
システム開発におけるプロジェクト体制図
プロジェクト体制図とは、プロジェクトのメンバー間の関係性や、担当について図で表したものです。
プロジェクト内部の体制は目には見えない抽象的なものであるため、自分がどの業務を担当すればいいのか、誰に指示を貰えばいいのかが分からず、作業効率が低下してしまうことが多くあります。
システム開発の際に、プロジェクトの体制を図に書いて可視化することで、各メンバーが自分の立ち役割を視覚的に理解するのに役立ちます。
各メンバーの役割や業務範囲が明確になることで、作業漏れや認識齟齬のリスク低減にも繋がります。
プロジェクトでは、メンバー同士の連携が成功に大きく関わってくるため、こうした体制図の作成は重要かつ効果的です。
プロジェクト体制図はいつ作成する?
プロジェクト体制図は、プロジェクトの目的と、そのゴールを決めたタイミングで、プロジェクト計画書の一部として作成します。
目的が明確になっていないタイミングで体制図を作り始めても、必要な人材やリソース配分の判断材料が不十分なため、有効なプロジェクト体制図は作成出来ません。
まずは、システム開発プロジェクトの目的やゴールを明確にすることが先決です。
システム開発の規模や納期などのスケジュールに合わせて適切な体制を取り、過不足なくプロジェクトを完遂出来るように作成しましょう。
システム開発におけるプロジェクト体制図の必要性とは?
システム開発の際にプロジェクト体制図を作成することで、業務上起こりうる様々なリスクを軽減させることが出来ます。
プロジェクト体制図の必要性を、いくつかご紹介します。
プロジェクトへの参加メンバーがわかりやすい
システム開発のプロジェクトに誰がどんな役割で参加しているのかが、体制図があれば一目で分かります。
また、体制図があることで、問題が発生した場合に、責任の所在や対応にあたる担当者などについて、メンバー全員の認識を統一することが出来ます。
プロジェクト説明がしやすくなる
プロジェクト体制図があることで、システム開発プロジェクトの説明が容易になります。
新しいプロジェクトを開始する際、最初に行われるキックオフミーティングでは、プロジェクトの内容や各メンバーの業務内容について話し合う場面があります。この際に、プロジェクト体制図があることで、各人の役割や所属するチーム等が把握しやすくなります。
メンバー間の指揮命令系統を定義できる
システム開発のプロジェクトメンバーが多くなるにつれて、指揮命令系統(レポートライン)が不明瞭になってしまうリスクが高くなります。
指示を受ける側も、誰に相談すべき内容かが分からず作業効率が低下してしまい、スケジュール遅れやデグレード等のリスクに繋がります。
デグレードについては、こちらの記事でも詳しく紹介しているのでぜひご確認ください。
プロジェクト体制図の書き方
プロジェクト体制図は、その名の通りプロジェクトの体制が理解できるような図でなければなりません。
以下の点に注意して、誰が見ても把握出来るプロジェクト体制図の作成を心がけましょう。
1. わかりやすいプロジェクト名称
プロジェクト名称は分かりやすい名称にしましょう。
システム開発のプロジェクトであれば、システム名をプロジェクト名にするなど、何のために結成されたプロジェクトかが一目で分かるようにします。
2. プロジェクトの目的やチームの運営方針を記入
プロジェクトの目的や、チームの運営方針を決定して、プロジェクト体制図に合わせて記入しておきましょう。
プロジェクトによっては、後からプロジェクトに参加するメンバーが出てくる場合もあります。
後から参加したメンバーが、プロジェクト体制図を一目見るだけで、プロジェクトの目的や各チームの運営方針が理解出来るような書き方を心がけましょう。
3. 役割や権限をグループ・階層に記入
プロジェクト内のそれぞれの役割やグループ、階層は明確に記入しておきましょう。
例えばプロジェクト内に「製造G」「品質管理G」「サービスG」など複数のグループが存在する場合、それらを一つの箱の中にまとめて書いてしまうと、それぞれのメンバーの役割や、指揮命令系統が分かりづらくなってしまいます。
グループ毎の体制については、統合して記載せずに、分けて記載しましょう。
プロジェクト体制図を作成するときのポイント
実務に合った、役に立つプロジェクト体制図を作成するポイントをご紹介します。
体制図はピラミッド状に作成する
体制図は、各役割・人員の指揮命令系統を明示するためにも、ピラミッド状に作成しましょう。
これは階層型組織構造とも呼ばれ、組織構造を表す図として最も広く使われています。
役割は明確に記載する
役割は曖昧でなく、明確に記載しましょう。
「グループ名が記載されていても、何が目的のグループか分からない」「役割が曖昧なため、何をすればいいのか分からない」といった問題を解消するものがプロジェクト体制図です。
プロジェクト体制図を見ることで、各メンバーの所属や役割が分かるものにしましょう。
また、長期のシステム開発プロジェクトになる場合、途中でメンバーの役割が変わったり、後からメンバーが追加される場合もあります。
プロジェクト体制図と現状に齟齬が生まれないよう、常に最新の状態にアップデートしておきましょう。
指揮命令系統は一本化する
各メンバーに指示を与えるのは誰か、指揮命令系統は明確にするとともに一本化しましょう。
複数の方向から指示があると、どの作業を優先するべきなのかが分からない他、相反する指示を受けた場合は混乱してしまい、作業効率が低下します。
指揮命令系統は一本化して、プロジェクト体制図に分かるよう記載しておきましょう。
プロジェクトの責任者は複数人にしない
プロジェクトの責任者は複数人にしてはいけません。
プロジェクト内に複数のグループが存在する場合、各グループのリーダーをそれぞれ責任者として横並びにしてしまうことがあります。
グループ内を取りまとめるのはグループリーダーの役割ではありますが、最終的に各グループの情報はプロジェクトマネージャーに集約するようにしましょう。
一貫性を保つためにも、上下関係を明確にして、必ず最高責任者を決めましょう。
同一人物を複数箇所に配置する場合は注意書きを書く
人的リソースの状況によっては、複数のグループに同一人物が所属して業務を兼任する場合があります。
その場合は、兼任していることを注意書きとして記載しておき、記載ミスではないことを示しておきましょう。
プロジェクト体制図を作成してみよう
プロジェクト体制図は、プロジェクトの目的に向かって、誰がどの役割で作業するか、また指揮命令系統はどうなっているかを明確にするためには重要なツールです。
特に大きなシステム開発のプロジェクトにおいては、プロジェクトの体制を明確にしておくことは、不要な混乱を避けるためにも重要です。
分かりやすいプロジェクト体制図があることで、作業の報告や進捗確認等もしやすくなるため、作業効率も上がります。
システム開発の際は、ポイントをおさえて、プロジェクト体制図を作成してみましょう。