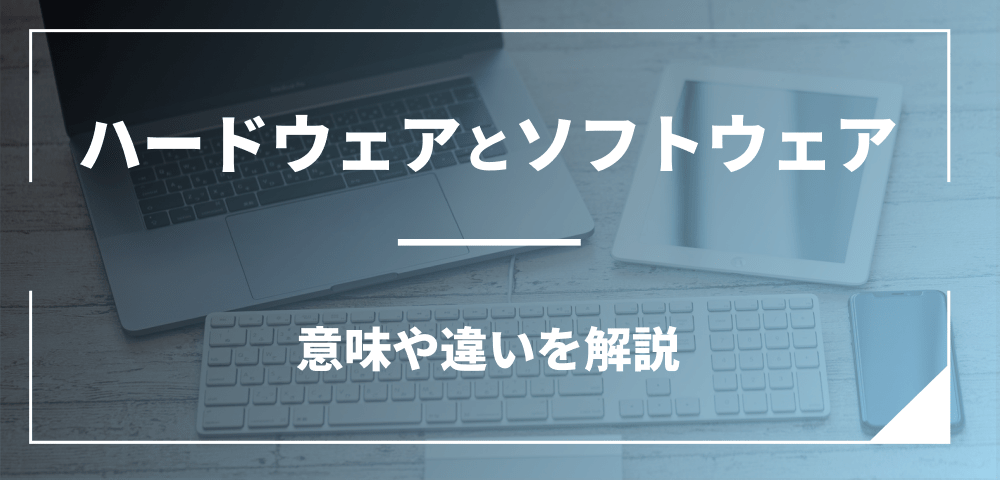私たちが普段利用するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで構成されています。
どちらも聞き覚えのある言葉ですが、ハードウェアとソフトウェアは具体的にどう違いがあるのか、それぞれ明確になっていると、開発業務もよりスムーズになります。
今回は、ハードウェアとソフトウェアの違いについて、またビジネス用語としてよく使われる、ハード面とソフト面という言葉についてご紹介します。
ハードウェアとは?
ハードウェアとは、コンピュータを物理的に構成する、周辺機器や回路などの装置の総称です。
メモリやCPU、コンピュータの周辺機器と呼ばれるものは全てハードウェアです。
、制御装置、演算装置、記憶装置、入力装置、出力装置の「コンピュータの5大装置」に分けられるそれぞれの機械と、それらをまとめて収める筐体などがハードウェアに該当します。
コンピュータの5大装置についての説明は、こちらの記事でも詳しく紹介しているのでぜひご確認ください。
ハードウェアの種類について、代表的なものをいくつかご紹介します。
・パソコン
パソコンとは、パーソナルコンピュータ(Personal Computer)の略で、様々な用途での個人利用を可能とした多目的なコンピユータになります。
パソコンは、デスクトップ型とノート型にそれぞれ分けられており、画面を出力するためのディスプレイや、文字入力のためのキーボード、ファイルやウィンドウを選択するためのマウスなど、複数のハードウェアが集まって構成されています。
・スマートフォン
スマートフォンは、持ち運ぶことが出来るコンパクトなタイプのコンピュータです。
ディスプレイ上に表示された情報を指でタッチしたりなぞったりすることで、アプリケーションを操作することが可能です。
スマートフォンは小さな端末の中に、ディスプレイやスピーカー、内部にはCPU、メモリなどのハードウェアが集約されています。
・タブレット
タブレットは、スマートフォンよりも一回り大きいタイプのコンピュータです。
ディスプレイを指で操作出来る点はスマートフォンと変わりませんが、外部のキーボードやマウスなどのハードウェアを接続して、パソコンさながらに利用できるタイプの製品もあります。
・メインフレーム
メインフレームは、官公庁や企業の基幹システムを動かすために利用されていた、大型のコンピュータです。
大人数の業務をメインフレーム一台で管理・運用していたため、絶対に止まらない、故障しないといった信頼性を実現するために高性能なものが造られてきました。
現代では高性能な個人用パソコンが普及しているため、業務も各自のパソコンを利用して行うようになりましたが、各企業が情報を集約するための中心的なコンピュータとしては、今現在も利用が続いています。
ソフトウェアとは?
ソフトウェアとは、コンピュータを動作させるための命令を、コンピュータが理解できる言語で記述したプログラムのことを指します。
ハードウェアの機器類を制御するためにもソフトウェアは必要となります。
適切なソフトウェアが搭載されているからこそ、私たちは普段パソコンやスマートフォンを操作出来るようになっています。
また、システム開発の現場ではソフトウェアを開発するケースが多いため、ソフトウェアにはどのような種類があるのか、理解しておくことは重要です。
今回は、システムソフトウェアとアプリケーションソフトウェアについてご紹介します。
・アプリケーションソフトウェア
アプリケーションソフトウェアは、特定の処理や機能を実現するために作られたソフトウェアのことで、アプリと呼ばれることもあります。
例えば、Webページを閲覧するために必要な、GoogleChromeやSafariなどのWebブラウザーや、資料を作るためのワープロソフトや表計算ソフト、クラウド上で動くWebシステムなど、私たちが普段利用しているものはほとんどがアプリケーションソフトウェアに該当します。
・システムソフトウェア
システムソフトウェアは、ハードウェアを直接操作・制御して、コンピュータの動作をサポートするためのソフトウェアです。
ハードウェアの管理やプロセス管理といったコンピュータの制御を行うOS(Operating System)ソフトや、アプリケーションソフトウェアとOSの間で、それぞれの複雑な処理を実現させるためのミドルウェアなどがシステムソフトウェアに該当します。
ハードウェアとソフトウェアの違いとは?
ハードウェアとソフトウェアは混同されがちですが、大きな違いは、目に見える実体のあるものかどうかです。
ハードウェアはマウス、キーボード、ディスプレイなど、コンピュータを操作するために利用する、実体のあるものですが、ソフトウェアはコンピュータ内部で動くプログラムであるため、実体はなく、目で見ることは出来ません。
また、硬い金属を意味するハードウェア(hardware)に対して、実体がない柔らかいものとしてソフトウェア(software)という言葉が造られています。
これらのことから、ハードウェアとソフトウェアはそれぞれコンピュータの利用に欠かせないものではありますが、対極的な存在であると言えます。
よく使う「ハード面」「ソフト面」の意味って?
ハードウェア、ソフトウェアという言葉から派生して、ハード面、ソフト面という言葉が使われるようになりました。
ハード面、ソフト面はシステム開発の分野としてだけでなく、ビジネス上でも多用される言葉です。
それぞれの言葉の意味について、具体例を挙げて説明します。
「ハード面」の意味
ハード面とは、装置や道具、設備といった、ビジネス上で形があるもののことを指します。
例えば、スーパーマーケットを新たに開店する場合
- 店舗にはバリアフリーのために、スロープや自動ドアなどを設置する
- レジスターなどのPOS設備は最新のものを導入する
- 商品の陳列棚は適切な高さのものを導入する
- 店内には明るい照明を付ける
- 看板は大きくてインパクトのあるものを設置する
など、形があるものに対して何かしらの対応を行うことを、ハード面の対応を行う、などと言う場合もあります。
「ソフト面」の意味
ソフト面は、形があるハード面に対して、社内の情報や人材の教育など、ビジネス上で無形のものを指します。
前述のスーパーマーケットの例を挙げると
- 従業員の接客やレジの研修を行う
- 従業員のシフト管理や、アルバイトの募集、面接を行う
- 各作業場へ適切な人員・適切な人数を配置する
- 従業員のメンタルケアを行う
- 商品の安全管理・衛生管理を行う
など、形がないものに対して何かしらの対応を行うことを、ソフト面の対応を行う、などと言う場合もあります。
具体的に何をハード面、もしくはソフト面とするかは、その職種や現場によって詳細は異なります。
【まとめ】ハードウェアとソフトウェアの意味・違いを理解しよう
ハードウェアとソフトウェアは、それぞれの性質に大きな違いがありますが、どちらもシステムには必要不可欠な要素です。
ハードウェアはソフトウェアを入れるための機械であり、ソフトウェアはハードウェアがあってこそ動作します。
この2つはお互いに密接な関係になっているので、意味や違いは正確に把握しておきましょう。